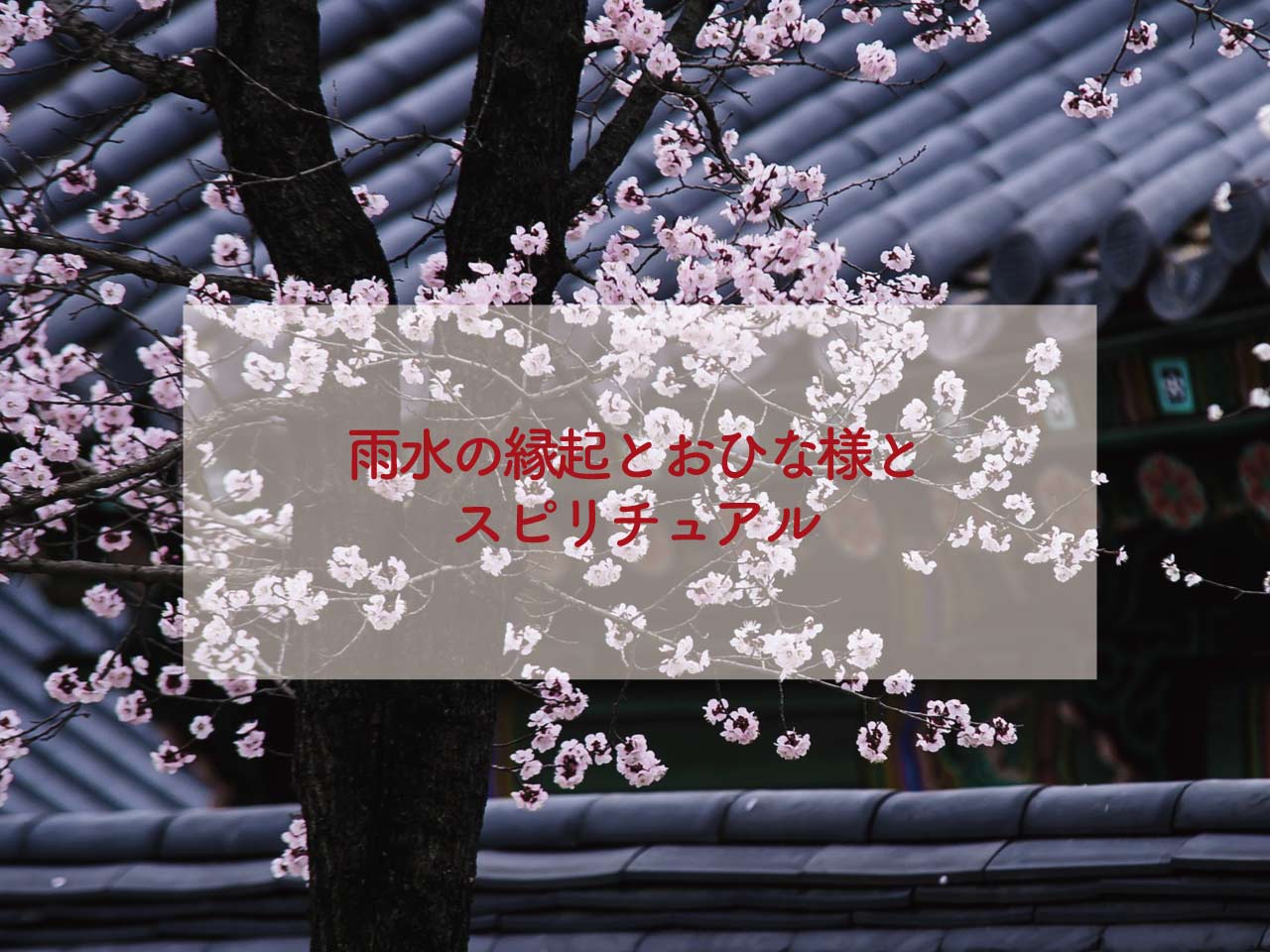
二十四節気の雨水…立春や立冬、立夏、冬至、夏至といった有名どころと違ってあまり聞いたことがないかもしれません。
雨水は雪が雨になる日…立春の終わりです。この雨水の縁起やスピリチュアルについてやお雛様との関係についてご紹介です。
雨水の読み方は「うすい」
雨水の読み方は「うすい」です。
雨水とは 簡単に
雨水とは二十四節気の一つで立春の次になります。
簡単にいうと、雨水の意味はそのまま「雨(あめ)」で「空から降る雪が雨に変わり、氷が水になって雪解けが始まる時期」のことなのです。
立春から始まった春がとうとう雪を溶かして雨が降り始める…それが雨水です。
雨水と二十四節気
二十四節気は、太陽が動く道である黄道を24等分して名称をつけたもので、季節を知るために用いられます。立春は「二十四節気」の最初の節気です。
雨水は太陽黄径330度の位置に来た日と定義されており、例年2月19日頃です。
二十四節気(にじゅうしせっき)は、1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けますので、それぞれ大まかに15日間隔になります。
| 季節 | 二十四節気名 | 月 | 新暦の日付 |
|---|---|---|---|
| 春 | 立春(りっしゅん) | 1月節 | 2月4日頃 |
| 雨水(うすい) | 1月中 | 2月19日頃 | |
| 啓蟄(けいちつ) | 2月節 | 3月5日頃 | |
| 春分(しゅんぶん) | 2月中 | 3月21日頃 | |
| 清明(せいめい) | 3月節 | 4月5日頃 | |
| 穀雨(こくう) | 3月中 | 4月20日頃 | |
| 夏 | 立夏(りっか) | 4月節 | 5月5日頃 |
| 小満(しょうまん) | 4月中 | 5月21日頃 | |
| 芒種(ぼうしゅ) | 5月節 | 6月6日頃 | |
| 夏至(げし) | 5月中 | 6月21日頃 | |
| 小暑(しょうしょ) | 6月節 | 7月7日頃 | |
| 大暑(たいしょ) | 6月中 | 7月23日頃 | |
| 秋 | 立秋(りっしゅう) | 7月節 | 8月8日頃 |
| 処暑(しょしょ) | 7月中 | 8月23日頃 | |
| 白露(はくろ) | 8月節 | 9月8日頃 | |
| 秋分(しゅうぶん) | 8月中 | 9月23日頃 | |
| 寒露(かんろ) | 9月節 | 10月8日頃 | |
| 霜降(そうこう) | 9月中 | 10月24日頃 | |
| 冬 | 立冬(りっとう) | 10月節 | 11月7日頃 |
| 小雪(しょうせつ) | 10月中 | 11月22日頃 | |
| 大雪(たいせつ) | 11月節 | 12月7日頃 | |
| 冬至(とうじ) | 11月中 | 12月21日頃 | |
| 小寒(しょうかん) | 12月節 | 1月5日頃 | |
| 大寒(だいかん) | 12月中 | 1月21日頃 |
雨水の期間は2月19日〜3月4日頃
雨水の期間は2月19日〜3月4日頃にあたります。立春から数えて15日目が雨水となり、その後の15日間が雨水の期間となるのです。雨水の次は啓蟄…雨水が終われば土中で冬ごもりをしていた生き物たちが目覚める頃となるのです。
| 2024年の雨水 | 2024年2月19日(月曜日) |
| 2025年の雨水 | 2025年2月18日(火曜日) |
| 2026年の雨水 | 2026年2月19日(木曜日) |
| 2027年の雨水 | 2027年2月19日(金曜日) |
| 2028年の雨水 | 2028年2月19日(土曜日) |
| 2029年の雨水 | 2029年2月18日(日曜日) |
| 2030年の雨水 | 2030年2月19日(火曜日) |
雨水と春一番と雨一番
雨水は雪解けの季節、山に積もった雪が解けて田畑を潤し、川や湖に張っていた氷も解け、春一番が吹く季節です。草木が芽生える頃で、昔から農耕の準備を始める目安とされてきました。
春一番は雨水の頃に
気象庁では、冬から春への移行期に初めて吹く暖かい南よりの強い風を「春一番」としています。 2022年の春一番は、2月15日に北陸地方、3月5日に関東と東海地方、3月18日に九州南部・奄美地方で観測されました。
ちょうど雨水の期間である2月19日〜3月4日頃ですね。この暖かい風と共に農作業を始めるのです。
雨一番と雨水
雨一番という言葉を知らない方も多いでしょう。これは北海道で使われる言葉で、立春のあと初めて雪が混じらずに降る雨のことを言います。
北海道では年明けから降り続けた雪が初めて雨に変わる日として、立春や節分、雨水よりも「春」を感じる日になります。春一番の代わりに気象庁の初代広報室長だった平塚和夫さんが昭和60年(1985年)に作った言葉だそうで、素敵な言葉ですね。
この雨一番は、残念なことに雨水の時期(2月19日〜3月4日頃)には降りません。ぎりぎり函館や江差といった道南で3月2〜5日に、札幌では3月15日前後、釧路といった道東では3月20日前後に降るのです。
雨水と三寒四温
この雨水の時期には雪が雨に変わり、春一番も吹いて暖かくなりますが、まだまだ寒い日も多いものです。
三寒四温は冬の時期に寒い日が3日くらい続くと、そのあとに比較的暖かい日が4日続くという意味の言葉で、寒暖の周期を表しています。 もとは中国の東北部や朝鮮半島北部で冬の気候を表す言葉として用いられましたが、現代の日本では春の始まりのこの時期で使われることが多くなりました。
透き通るように晴れ渡る空の寒さと、降る雨の暖かさを感じる言葉ですね!
雨水と雛人形とひな祭り
この雨水の日の行事といえば「雛人形を飾る」になるでしょう。
雨水に雛人形を飾ると良縁に恵まれるという風習があります。
3月3日の雛祭り(桃の節句)は上巳の節句とも言われ、雛人形を飾って子どもの健やかな成長を祈るお祝いです。
この雛人形には「いつから飾る」という明確なルールはなく、地方や家庭でのやり方がとても違うものです。一般的には立春から2月中旬くらいまでに飾り、前日に飾る「一夜飾り」は避けるほうがいいと言われています。
この雛人形を飾る日をこれまで悩んでいた人は、雨水に出すのがおすすめです。
どうして雨水に雛人形を飾ると良縁に恵まれるのか由来
雨水に雛人形を飾ると、良縁に恵まれるというのは、雛祭りは水に関係する行事で、雛人形は厄を移した人形を水に流していたことに由来するためです。
水が豊かになる雨水に雛人形を飾り始めたら、水が良縁がもたらすと考えたからなんだそうですよ!
雨水と縁起とスピリチュアル
雨水は立春から15日後になり、とうとう雪は止み暖かな春の雨がふり、梅の花が咲き桜の蕾が膨らみ出す時期です。
この時期はまさに自然が動き始める時期になります。それは同時に運気も活発になるということ。以前、立春のスピリチュアルで節分は運気が変わることを紹介しましたが、変わり始めた運気がどんどんスピードをつけて動き始めるのが、この雨水の時期なのです。冬の間眠っていた何もかもが少しずつ目を覚まして、小鳥も動物も本格的な春に向けて行動を開始します。
この雨水の時期、運気はとても波がありますが、いい方向に向かえるように過ごしてくださいね!
またこの日はひな人形を出すと縁起の良い日!良縁に恵まれますよ!
雨水と七十二候
雨水は第四候から第六候の期間になります。七十二候についてはこちらの記事を読んでね!
| 雨水の七十二候 | 期間 | 読み方 |
|---|---|---|
| 第四候「土脉潤起」 | 2/19~2/23頃 | つちのしょううるおいおこる |
| 第五候「霞始靆」 | 2/24~2/28頃 | かすみはじめてたなびく |
| 第六候「草木萌動」 | 3/1~3/4頃 | そうもくめばえいずる |
雨水の七十二候、第四候「土脉潤起 (つちのしょううるおいおこる)」 2/19~2/23頃
七十二候の雨水の初候は第四候「土脉潤起(つちのしょううるおいおこる)」になります。
あたたかな雨に大地が潤い活気づく頃、降っていた雪が春の雨に変わり、凍てついた大地もゆっくりと潤い、池の氷も溶け始めます。忍び寄る春の気配に眠っていた植物が芽吹き始める季節です。
土は雪解け水でぬかるみ、日差しが暖かな春の匂いを湧き立たせます。春の季語はこの土を歌った「春の土」「土恋し」「土匂う」「春泥」などがあります。
雨水の七十二候、第五候「霞始靆 (かすみはじめてたなびく)」 2/24~2/28頃
七十二候の雨水の次候は第五候「霞始靆(かすみはじめてたなびく)」です。春の霞がたなびき、山々の裾野にうっすらと広がる様子が思い浮かびますね!
「靆=たなびく」は、霞や雲が層をなし薄く長く漂っている様子を表しています。春になると、冬場の乾燥から打って変わって、大気中に細かな水滴や塵が増え、遠くの景色がぼんやりとかすむ「霞」が見られることがあります。「霞」は春の季語、童謡「朧月夜」の一節にも出てきます。
「菜の花畠に入り日薄れ 見わたす山の端 霞ふかし」は長野県出身の高野 辰之の原体験なのでしょう。長野の奥穂高岳や槍岳が続く美しい山並みと霞が思い浮かびます。
雨水の七十二候、第六候「草木萌動 (そうもくめばえいずる)」 3/1~3/4頃
七十二候の雨水の末候は第六候「草木萌動(そうもくめばえいずる)」になります。草木が萌え出す頃を表していて、暖かい日差しに誘われて地面や木の枝から萌黄色の小さな命が一斉に芽吹き始めます。
この時期の雨は「木の芽雨」、吹く風は「木の芽風」と呼ばれ、木の芽が膨らむのを助助けてくれるんですって!
雨水の行事と食べ物
雨水の時期の行事は雛人形を出すことになりますが、それ以外に特別な行事はありません。あえていうなら、この雨水は梅の花が見頃を迎えるため、全国各地の梅の名所では「梅まつり」が開催されるということでしょう。
現代では花見といえば「桜」一択ですが、奈良時代の花見は梅だったとか…これが梅に変わった明確な理由はないようですが、寒さに震える梅よりも、暖かな陽気の桜でどんちゃん騒ぎがしたかったのかもしれませんね!
この雨水に行事食はありませんが、もしされるならこの梅にちなんで、梅を使ったお料理やご飯を梅の形にした花形ご飯がおすすめですよ!
お雛様のこと、雛人形のこと
お雛様についてもっと知りたかったら、下記の記事も読んでね!


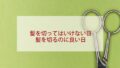



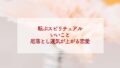

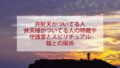




コメント 成功の口コミや疑問…読んでね!
インスタにありました梅の花の待ち受けは、どこにあるのでしょうか?
また待ち受けにすると、どのような効果があるのでしょうか?
インスタを見ていただいてありがとうございます。
このページに追加しておきました!
梅の画像は厄除けになるって言われています!
願いが叶いますように!