
9月9日は重陽の節句です。重陽の節句はひな祭りの上巳の節句やこどもの日の端午の節句、七夕の節句と違ってあまり日本では有名ではありませんね。
日本では「苦しむ」や「苦労」という言葉と「9」の音が同じなので、あまり良い印象のない「9」の日に行われます。
この重陽の節句で厄を落として開運しましょう!
重陽の節句とは
重陽の節句についてです。
重陽の節句の読み方は「ちょうようのせっく」
重陽の節句の読み方は「ちょうようのせっく」です。
重陽の節句とは
重陽の節句は五節句の一つで9月9日に行われます。菊を浮かべた酒や菊の花を飾って長寿を願う日です。
五節句とは
端午の節句と同じく、五節句にあるのは下記になります。
- 人日(じんじつ)の節句(1月7日)、七草粥を食べて1年の無病息災を願う
- 上巳(じょうし)の節句(3月3日)雛人形を飾って女の子の成長と良縁をねがう桃の節句、お雛祭り
- 端午の節句(5月5日)鎧兜や鯉のぼりを飾り邪気を払って男の子の武運長久を祈る
- 七夕(しちせき)の節句(7月7日)笹に短冊を吊るして願い事をする、七夕様。(お盆とする説もあります)
- 重陽(ちょうよう)の節句(9月9日)菊を浮かべた酒や菊の花を飾って長寿を願う
重陽の節句はどんな日
重陽の節句は平安時代初期に、中国からほかの五節句とともに日本に伝わりました。平安貴族を中心に四季を愛でて楽しむ行事として広まったのです。
旧暦の9月9日は、現在の10月中旬ごろに当たります。10月の中旬は菊の花が美しく咲き、見頃を迎える時期になります。日本各地で菊まつりが開催される時期ですね!
菊は皇室の紋章としても知られていますが、邪気を払う力をもつ霊草と信じられていたます。そのため重陽の節句には菊の花を観賞し、菊の花を漬けた酒を飲んで、無病息災や不老長寿を願ったそうです。
重陽の節句は菊の節句
重陽の節句は菊を鑑賞したり食用したりするため「菊の節句」とも呼ばれ、江戸時代になると庶民の間でも広く親しまれる季節の行事となりました。
ところが明治初期に政府が旧暦から新暦へ改暦の公布を行い、五節句廃止令を出したのです。重陽の節句以外の五節句は、新暦へと日付が変わっても行う人が多かったのですが、新暦の9月9日はまだ菊の咲く時期ではありません。
そのため、現在のようにあまり知られない行事となったのかもしれませんね。
なぜ皇室の紋章は菊になったのか
鎌倉時代の後鳥羽上皇が菊の紋を非常に好み、愛用したのが始まりと言われています。その後、深草天皇、亀山天皇、後宇多天皇も菊の紋を用いたことで、皇室を示す紋として定着しました。
菊は中国から「不老長寿の霊草」として輸入されてきたものです。非常に香りが良く美しい佇まいで、実際に食用菊には豊富なビタミンと殺菌・解毒効果がありますので、「不老長寿の霊草」も頷けますね!
9月9日の重陽の節句は不吉なスピリチュアル
中国では奇数のことを陽数といいます。陽数は縁起が良い日で、なかでも最も大きな陽数は「9」になります。このが「9」重なる9月9日を「重陽の節句」として、無病息災や子孫繁栄を願う祝いの宴を開いたことが起源とされています。
しかし中国風水では陽数が重なると災いが起こりやすく不吉だという考え方もあり、災いが起きないように9月9日には邪気を払う風習ができたのです。
確かに99だと不吉な感じがしますよね〜。
重陽の節句で厄落としと開運と食べ物
不老長寿の霊草と呼ばれる菊の花…この菊を愛でる重陽の節句では菊の花を使った厄落としや開運方法がたくさんあります。
この重陽の節句に食べたら開運するものもたくさんありますので、ぜひ試してくださいね!
重陽の節句の着せ綿
重陽の節句で最も有名なおまじないは「着せ綿」かもしれません。
というもので、これをすれば若さを保って長生きできると大変な人気がありました。和菓子でも「着せ綿」ありますね!
重陽の節句の菊酒
重陽の節句なら菊酒は外せません。飲めば不老長寿になるという菊酒です。
「菊酒」は、食用菊の花びらを蒸して冷酒に漬けることで花の香りが酒に移り、非常に雅な逸品です。
現代では菊酒はなかなか難しいですが、食用菊をお酒に浮かべて飲むのでもOKですよ!菊には高い殺菌・解毒作用があり、ビタミンも豊富です。
重陽の節句の栗ごはん
重陽の節句の時期に食べるものならやはり栗ごはんです。
重陽の節句の行事食と言ってもいいでしょう。栗の本格的な収穫時期には少し早いですが、旬の物になります。
栗ごはんを食べる風習は江戸時代から始まったといわれており、旬のものが好きな江戸っ子にとっては馴染み深い食べ物です。
菊には無縁な庶民の間では重陽の節句を「栗の節句」と呼ぶ人も多かったとか。
重陽の節句の茄子は中風防止
重陽の節句に食べたいものは茄子になります。これは「くんち(9日)に茄子を食べると中風(ちゅうぶ)にならない」という言い伝えから始まったと言われています。
茄子の旬は7~9月の夏なのですが、9月ごろから収穫される「秋茄子」は特に美味しい茄子になります。
秋茄子は嫁に食わすな
「秋茄子は嫁に食わすな」という諺は「家の中では身分の低い嫁にこんな美味しいものを食べさせてはいけない」という捉え方もありますが、茄子には毒性のアルカロイドが微量含まれていて、食べすぎると食中毒のような症状が出ることもあります。
あまりの美味しさに大量に摂取してしまうと、体には毒…そのため大切なお嫁さんに食べさせてはいけない、という意味でもあります。
重陽の節句のお祭り「くんち」「後の雛(のちのひな)」「菊合わせ」
あまり馴染みのなくなってしまった重陽の節句ですが、現代の日本でもさまざまな形で行事が残っています。
重陽の祭り「くんち」
重陽の節句は秋の節句となったので、作物の収穫祭として名前を変えながら全国各地で行われています。
有名なのは九州地方の「くんち」でしょう。「くんち」とは九州の方言で9日を意味しており、収穫を感謝して行われる秋祭りとなっています。
「長崎くんち」「唐津くんち」「博多おくんち」を「日本三大くんち」と呼び、なかでも長崎くんちは400年近く続く諏訪神社の礼祭で、国の重要無形民俗文化財にも指定されています。
重陽の節句「後の雛(のちのひな)」
3月3日の上巳の節句・桃の節句で飾った雛人形を片付けた後、9月9日の重陽の節句に再び飾ることで長寿を願う行事が「後の雛(のちのひな)」になります。
桃の節句は成人前の女の子の成長や幸福、結婚を願うのですが、菊の節句である重陽の節句は大人の女性の健康や長寿を願います。
「大人のひな祭り」ですね!
この「後の雛(のちのひな)」は大人の女性の健康や長寿を願うだけではなく、高価な雛人形を1年間しまい続けてカビたり害虫がついたりしないように、冬が来る前の9月に風を通しておく意味もあります。
重陽の節句「菊合わせ」
平安時代、重陽の節句で貴族が菊の花を愛でながら詩を読み合うことを「菊合わせ」と呼びました。この風習が育てた菊の花を持ち寄って美しさを競う菊合わせとなったのです。
現代では菊の盛りである10月から11月にかけて、各地で菊まつりが行われていますね!
重陽の節句と枕草子
最後に重陽の節句について書かれた枕草子の一文を紹介します。
暁がたより 雨すこし降りて
菊の露も こちたうそぼち
おほひたる綿など
もてはやされたる
つとめては、やみにたれど
曇りて、ややもすれば
降り落ちぬべく見えたる
をかし枕草子より
これは現代語にすると下記のようになります。
菊の花を覆った綿も
しっとり濡れて
移り香が強く薫る早朝にはやんだ雨
まだ曇っていて、ともすれば
雨が落ちてきそうな天気は
風情がある
枕草子でも「着せ綿」が歌われていますね!
菊の待ち受け
重陽の節句に菊の待ち受け、いいですよ!
邪気払いに菊の待ち受け、背景画像
菊は魔除けに邪気も払うと言われています!
花言葉は恋の勝利、紫の菊の待ち受け、背景画像
菊は「高貴」や「高尚」、そして紫の菊には「恋の勝利」や「夢が叶う」という花言葉があります。
菊は不老長寿の霊草とも言われた高貴な花、きっと恋が叶いますよ!

デイジー雛菊の待ち受け
デイジーの花言葉は「純潔」「美人」「平和」「希望」「あなたと同じ気持ち」幸せになれそうですね〜!


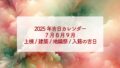
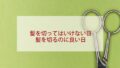

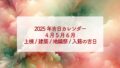



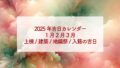






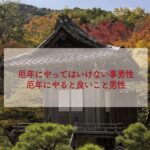
コメント 成功の口コミや疑問…読んでね!
こんばんは
重陽の節句は厄落としに髪の毛切るのはありなんですか?
それとも不吉だから辞めた方がいいんですか?
重陽の節句に厄落とし…いいと思いますよ!
ただ今日は先勝なので午前中の方がいいかもです。
もしくは「先勝は午後2時から午後6時までが凶」とされていますので、むしろ6時以降にするのもいいでしょう。
願いが叶いますように!