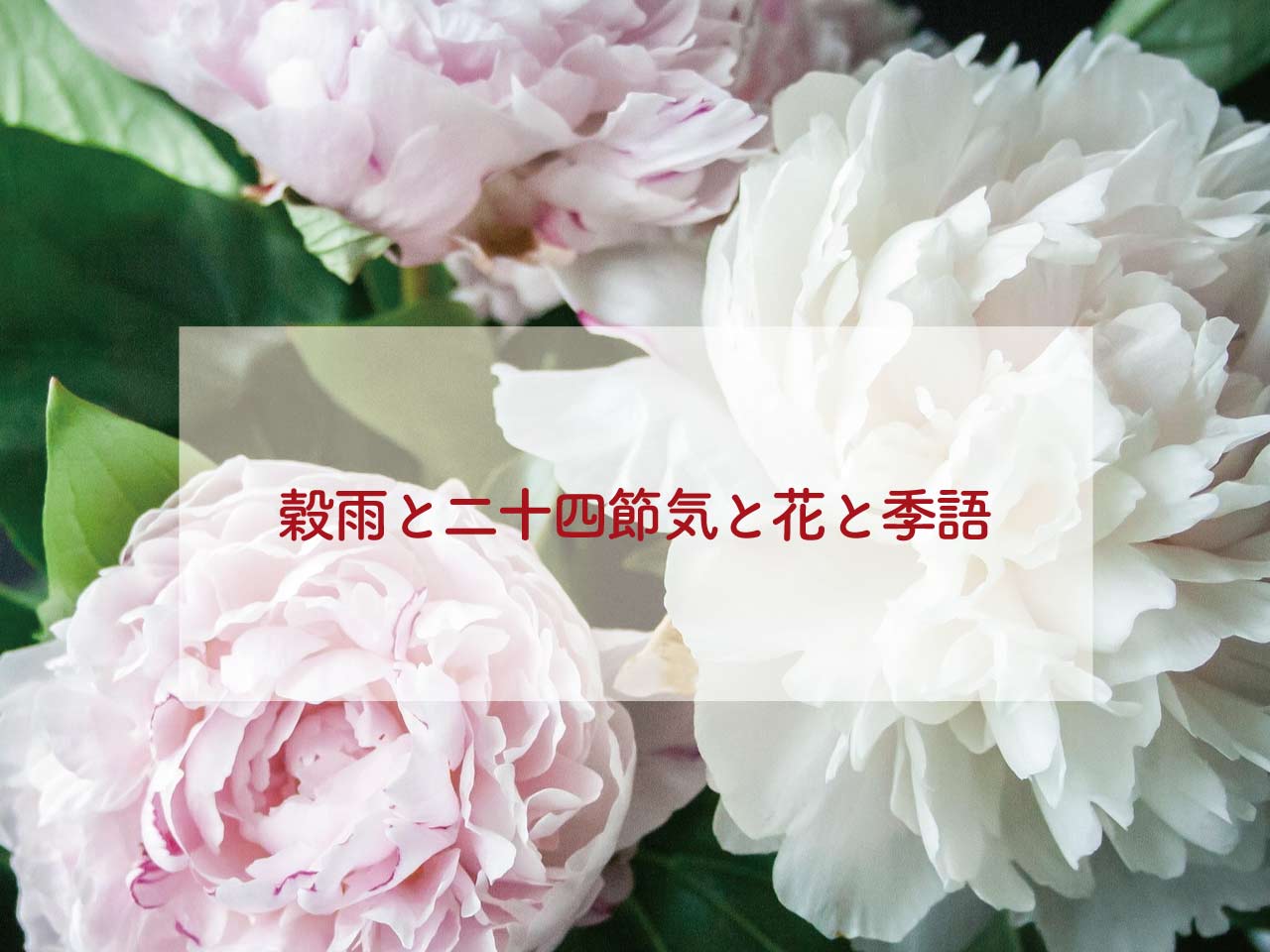
4月20日ごろは二十四節気の穀雨になります。
「夏も近づく八十八夜」はこの穀雨の時期の終わりごろにあたります。
穀雨とは簡単に2024
穀雨は簡単に言うと二十四節気の一つ、春の季節の6番目の節気です。
清明から十五日目に当たる4月20日ごろにあり、春の雨で田畑を潤し穀物の成長を促す時期と言われています。
清明と立夏の間にあたり、毎年4月20日ごろから5月4日ごろまでの期間を指します。この時期には、雨が多く降る季節で、春の草花や野菜は初々しく青々とした葉を伸ばす様子が見られます。過ぎ去る春を惜しむ時期でもあり、気温も上昇して初夏の訪れを感じられます。
2024年の穀雨
2024年の穀雨は4月19日となります。
2024年穀雨の期間
穀雨の期間は2024年は4月19日〜5月4日となります。
4月4日から始まった清明が4月19日に終わり、立夏が始まる5月4日前に終わることになります。
穀雨の読み方は「こくう」
穀雨の読み方は「こくう」です。
二十四節気一覧と穀雨
二十四節気(にじゅうしせっき)についてです。
二十四節気(にじゅうしせっき)とは
二十四節気(にじゅうしせっき)とは、1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けたものです。大まかに15日間隔ですね。
二十四節気は、小寒・大寒・立春・雨水・啓蟄・春分・清明・穀雨・立夏・小満・芒種・夏至・小暑・大暑・立秋・処暑・白露・秋分・寒露・霜降・立冬・小雪・大雪・冬至です。
二十四節気一覧
| 季節 | 二十四節気名 | 月 | 新暦の日付 |
|---|---|---|---|
| 春 | 立春(りっしゅん) | 1月節 | 2月4日頃 |
| 雨水(うすい) | 1月中 | 2月19日頃 | |
| 啓蟄(けいちつ) | 2月節 | 3月5日頃 | |
| 春分(しゅんぶん) | 2月中 | 3月21日頃 | |
| 清明(せいめい) | 3月節 | 4月5日頃 | |
| 穀雨(こくう) | 3月中 | 4月20日頃 | |
| 夏 | 立夏(りっか) | 4月節 | 5月5日頃 |
| 小満(しょうまん) | 4月中 | 5月21日頃 | |
| 芒種(ぼうしゅ) | 5月節 | 6月6日頃 | |
| 夏至(げし) | 5月中 | 6月21日頃 | |
| 小暑(しょうしょ) | 6月節 | 7月7日頃 | |
| 大暑(たいしょ) | 6月中 | 7月23日頃 | |
| 秋 | 立秋(りっしゅう) | 7月節 | 8月8日頃 |
| 処暑(しょしょ) | 7月中 | 8月23日頃 | |
| 白露(はくろ) | 8月節 | 9月8日頃 | |
| 秋分(しゅうぶん) | 8月中 | 9月23日頃 | |
| 寒露(かんろ) | 9月節 | 10月8日頃 | |
| 霜降(そうこう) | 9月中 | 10月24日頃 | |
| 冬 | 立冬(りっとう) | 10月節 | 11月7日頃 |
| 小雪(しょうせつ) | 10月中 | 11月22日頃 | |
| 大雪(たいせつ) | 11月節 | 12月7日頃 | |
| 冬至(とうじ) | 11月中 | 12月21日頃 | |
| 小寒(しょうかん) | 12月節 | 1月5日頃 | |
| 大寒(だいかん) | 12月中 | 1月21日頃 |
穀雨と八十八夜
「穀雨(こくう)」は、春季の最後の二十四節気で、田畑を潤し、穀物の成長を促す春の雨のことを指します。この時期は種まきの好期となります。雨が多いというわけではありませんが、穀雨以降、降雨量が増える傾向があります。春の終わりを感じる時期で、青々とした新芽が次々と伸びてくる様子を見ることができます。また、穀雨が終わると「八十八夜」と呼ばれる日が訪れ、茶摘みの最盛期となります。
八十八夜とは立春から数えて88日目
穀雨が終わる頃には、「八十八夜」がやってきます。2024年は5月1日です。この日は、立春から数えて88日目にあたり、夏の準備をする日とされています。茶摘みが最盛期を迎えるため、『茶摘み』という唱歌があります。八十八は縁起が良い数字で、この日に摘み取ったお茶を飲むと長寿になると信じられています。
農家にとっては、「八十八夜の別れ霜」という言葉もあり、この日を過ぎると農作物への霜害の心配がなくなり、本格的な農作業が始まります。また、「八十八」を重ねると「米」という字になるため、この日に農作業を始めるのが良いとされ、お祝いをする習慣があります。変わりやすい春の天気も安定して、日差しが強くなっていく5月。今年の夏も暑くなりそうですよ〜。
穀雨と縁起
穀雨は雨が多くなり始める時期です。春が終わり、青々と緑が伸び命が増えるこの季節は、縁起の良い出来事がなくとも素晴らしい季節です。
しかし、この穀雨の期間には八十八夜があります。
八十八夜の新茶は不老長寿の縁起物
八十八夜は、日本の節目の日の一つで、立春から数えて88日目にあたります。この日は、縁起が良い末広がりの「八」が2つ並ぶことから、長寿や繁栄を願う行事として親しまれています。特に、八十八夜の日に収穫される新茶は、不老長寿の縁起物として重宝され、そのお茶を飲むと一年を無病息災で過ごせると信じられています。
穀雨と花
この穀雨の時期の花をご紹介しますね!
穀雨の時期の花「百花の王」牡丹
穀雨の季節の花の一つである牡丹は、「百花の王」とも呼ばれるほど、その威厳や美しさに恵まれた花です。中国の北方が原産地であり、弘法大師が唐から持ち帰ったという伝承もあります。日本には江戸時代からボタンの名所があり、全国に100年以上200年以上の歴史を持つボタン園がたくさん存在しています。ボタンの人気の秘密は、寒さに強い特性と、絵画や着物の意匠にも愛される美しさにあると言われています。大輪で重厚感あふれる花は、「白王獅子」「麒麟の司」「金閣」などの堂々たる名前がつけられています。4月下旬から約1ヶ月、優雅な花姿を楽しむことができます。
穀雨の時期の花「子孫繁栄」藤
藤棚が設置される神社の境内や公園は、この時期には涼しげな場所となります。しかしその中で、蜜集めに夢中のハチに驚かされることもあるかもしれません。
日本の山野には、右巻きのノダフジと左巻きのヤマフジの2種類の蔓性のフジが自生しています。ノダフジは大阪の名所野田に由来する名前であり、寿命の長い植物で、1000年以上の長寿の木も存在します。蔓を広げてたくさんの花を咲かせ、縁起の良い「子孫繁栄」の木としても知られています。
穀雨の食べ物
穀雨の時期に旬を迎える野菜、魚をご紹介します。
春の旬の食材として、アスパラガスやさやえんどうが挙げられます。アスパラガスは、冬に根から蓄えた養分を春になってから伸び出した若い茎の野菜で、太くて穂先が固く絞まっているものが新鮮なものです。形がまっすぐで美しいものを選びましょう。さやえんどうは、早めに収穫したえんどうまめがさやごと食べられるもので、歯ざわりがよく、ほのかな甘味があります。炒め物や和え物におすすめです。
また、ヤリイカが旬を迎えます。身質が柔らかく、甘みがあるため、刺身にして楽しめます。鮮度に応じて身の色が透明、茶色、白と変化するので、透明のものが最も鮮度が高いとされています。
穀雨の七十二候
穀雨の七十二候をご紹介します。
| 二十四節気 | 候 | 日取り(頃) | 読み方 | 略本暦 | 宣明暦 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 意味 | 名称 | 意味 | ||||
| 穀雨 | 初候 | 4月20日〜24 | あしはじめてしょうず | 葭始生 | 葦が芽を吹き始める | 萍始生 | 浮き草が芽を出し始める |
| 次候 | 4月25日〜29 | しもやんでなえいづる | 霜止出苗 | 霜が終り稲の苗が生長する | 鳴鳩払其羽 | 鳴鳩が羽を払う | |
| 末候 | 4月30日〜5月4 | ぼたんはなさく | 牡丹華 | 牡丹の花が咲く | 戴勝降于桑 | 戴勝が桑の木に止って蚕を生む | |
七十二候については下記の記事も読んでね!

葭始生あしはじめてしょうず
葦は、「蘆」「荻」とも書かれ、「悪し(あし)」とも通じるため、「善し」とも読まれます。これは、日本独自の言霊思想に基づく忌み言葉の一つです。
忌み言葉は、縁起が悪く忌み嫌われる語であり、他にも梨を「有りの実」、披露宴の終わりを「お開き」、すり鉢を「あたり鉢」、また河童を「旅の人」というものがあります。
葦の茎は、竹と同様に中が空洞なので、軽くて丈夫です。葦簀や葦笛、茅葺き民家の屋根材などとして、古くから様々な形で利用され、人々の暮らしに身近な植物でした。
霜止出苗しもやんでなえいづる
穀雨の次候は「霜止出苗」となります。この頃になると、暖かくなって霜が降りなくなり、苗が健やかに育つ季節です。種まきから芽が出て、青々と茂る稲の苗を見ることができます。
ただし、4月下旬頃には「八十八夜の忘れ霜」という現象が起こることもあります。暖かさに誘われ、霜の心配を忘れかけた時に、思わぬ遅霜に見舞われることがあるのです。特に農業にとっては、霜は大敵です。茶葉の栽培においては、静岡県など一部地域では遅霜予報を行っており、茶業関係者が対策を行っています。10月下旬には、「霜降」へと移り変わり、再び霜が降り始める季節となります。
牡丹華ぼたんはなさく
七十二候が穀雨の末候に変わり、牡丹の花が咲き始める季節となります。
牡丹は直径10~20cmの大輪の花を咲かせ、紅・淡紅・白・紫などの様々な色を持ち、晩春から初夏にかけて見られます。もともとは薬草として中国から伝わり、平安時代には宮廷や寺院で観賞用として栽培されるようになり、今では俳句のテーマ、絵画や着物のモチーフとしてもよく登場します。
牡丹は、甘く上品な香りと格調高い姿から、「富貴草」「百花王」「花王」「花神」など褒め称える別名がたくさんあり、その美しさと香りを意味する「天香国色」もまた、牡丹の異名となっています。牡丹の花は約20日ほど楽しめることから「二十日草(はつかぐさ)」とも呼ばれます。
牡丹の花言葉は、「王者の風格」という名にふさわしいもので、その美しさから、中国では国の代表花にもなっています。


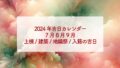

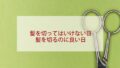


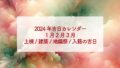
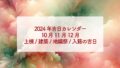
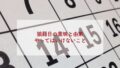

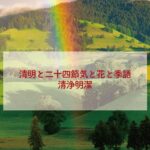

コメント 成功の口コミや疑問…読んでね!