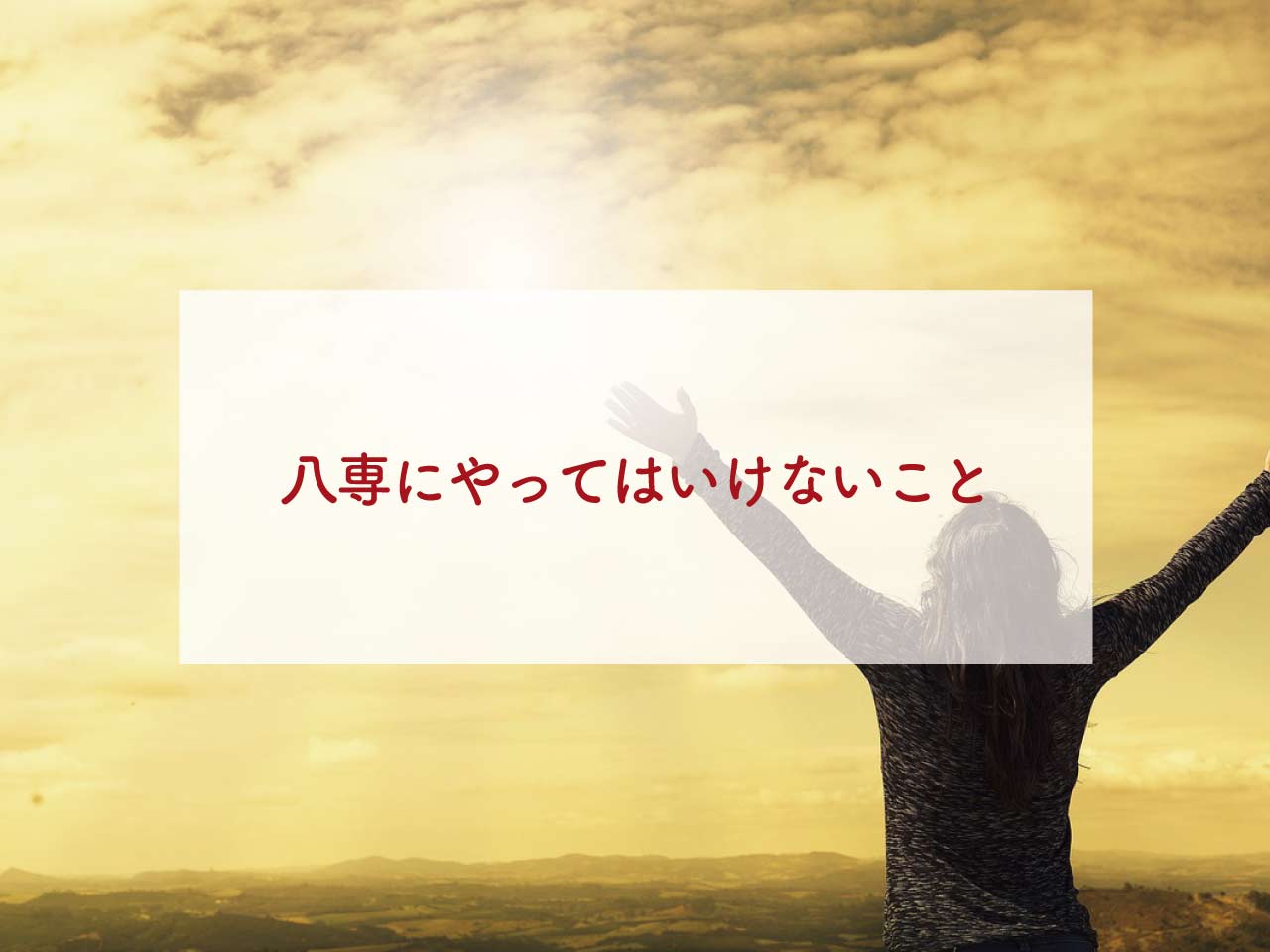
暦を見ると「八専」と書いてあるのを見ることがあるでしょう。
この「八専」とは何か、八専にやってはいけないことについてです。
八専とは
八専は選日法の一つであり、一般的にはあまり知られていない特別な日です。元来の意味は「吉はさらに吉となり、凶はさらに凶となる日」でしたが、現代では「凶はさらに凶となる日」と解釈されることが多く、その結果、凶日と見なされることが主流となりました。
この八専の由来は陰陽道や五行説にあります。陰陽の二十八宿から派生したもので、日本の暦注や選日の多くは陰陽五行説や十干十二支が元となっていますが、八専もその一つです。
2024年の八専の入りと終わりと間日
八専は基本的に壬子から癸亥までの12日間に五行の干支が重なる日に発生します。したがって、連続して発生することが特徴です。
1回目の八専と間日
| 日にち | 曜日 | 六曜 | 日干支 | 八専 |
| 2024年2月18日 | 日曜日 | 先負 | 壬子 | – |
| 2024年2月19日 | 月曜日 | 仏滅 | 癸丑 | 間日 |
| 2024年2月20日 | 火曜日 | 大安 | 甲寅 | – |
| 2024年2月21日 | 水曜日 | 赤口 | 乙卯 | – |
| 2024年2月22日 | 木曜日 | 先勝 | 丙辰 | 間日 |
| 2024年2月23日 | 金曜日 | 友引 | 丁巳 | – |
| 2024年2月24日 | 土曜日 | 先負 | 戊午 | 間日 |
| 2024年2月25日 | 日曜日 | 仏滅 | 己未 | – |
| 2024年2月26日 | 月曜日 | 大安 | 庚申 | – |
| 2024年2月27日 | 火曜日 | 赤口 | 辛酉 | – |
| 2024年2月28日 | 水曜日 | 先勝 | 壬戌 | 間日 |
| 2024年2月29日 | 木曜日 | 友引 | 癸亥 | – |
2回目の八専と間日
| 日にち | 曜日 | 六曜 | 日干支 | 八専 |
| 2024年4月18日 | 木曜日 | 赤口 | 壬子 | – |
| 2024年4月19日 | 金曜日 | 先勝 | 癸丑 | 間日 |
| 2024年4月20日 | 土曜日 | 友引 | 甲寅 | – |
| 2024年4月21日 | 日曜日 | 先負 | 乙卯 | – |
| 2024年4月22日 | 月曜日 | 仏滅 | 丙辰 | 間日 |
| 2024年4月23日 | 火曜日 | 大安 | 丁巳 | – |
| 2024年4月24日 | 水曜日 | 赤口 | 戊午 | 間日 |
| 2024年4月25日 | 木曜日 | 先勝 | 己未 | – |
| 2024年4月26日 | 金曜日 | 友引 | 庚申 | – |
| 2024年4月27日 | 土曜日 | 先負 | 辛酉 | – |
| 2024年4月28日 | 日曜日 | 仏滅 | 壬戌 | 間日 |
| 2024年4月29日 | 月曜日 | 大安 | 癸亥 | – |
3回目の八専と間日
| 日にち | 曜日 | 六曜 | 日干支 | 八専 |
| 2024年6月17日 | 月曜日 | 仏滅 | 壬子 | – |
| 2024年6月18日 | 火曜日 | 大安 | 癸丑 | 間日 |
| 2024年6月19日 | 水曜日 | 赤口 | 甲寅 | – |
| 2024年6月20日 | 木曜日 | 先勝 | 乙卯 | – |
| 2024年6月21日 | 金曜日 | 友引 | 丙辰 | 間日 |
| 2024年6月22日 | 土曜日 | 先負 | 丁巳 | – |
| 2024年6月23日 | 日曜日 | 仏滅 | 戊午 | 間日 |
| 2024年6月24日 | 月曜日 | 大安 | 己未 | – |
| 2024年6月25日 | 火曜日 | 赤口 | 庚申 | – |
| 2024年6月26日 | 水曜日 | 先勝 | 辛酉 | – |
| 2024年6月27日 | 木曜日 | 友引 | 壬戌 | 間日 |
| 2024年6月28日 | 金曜日 | 先負 | 癸亥 | – |
4回目の八専と間日
| 日にち | 曜日 | 六曜 | 日干支 | 八専 |
| 2024年8月16日 | 金曜日 | 先勝 | 壬子 | – |
| 2024年8月17日 | 土曜日 | 友引 | 癸丑 | 間日 |
| 2024年8月18日 | 日曜日 | 先負 | 甲寅 | – |
| 2024年8月19日 | 月曜日 | 仏滅 | 乙卯 | – |
| 2024年8月20日 | 火曜日 | 大安 | 丙辰 | 間日 |
| 2024年8月21日 | 水曜日 | 赤口 | 丁巳 | – |
| 2024年8月22日 | 木曜日 | 先勝 | 戊午 | 間日 |
| 2024年8月23日 | 金曜日 | 友引 | 己未 | – |
| 2024年8月24日 | 土曜日 | 先負 | 庚申 | – |
| 2024年8月25日 | 日曜日 | 仏滅 | 辛酉 | – |
| 2024年8月26日 | 月曜日 | 大安 | 壬戌 | 間日 |
| 2024年8月27日 | 火曜日 | 赤口 | 癸亥 | – |
5回目の八専と間日
| 日にち | 曜日 | 六曜 | 日干支 | 八専 |
| 2024年10月15日 | 火曜日 | 先負 | 壬子 | – |
| 2024年10月16日 | 水曜日 | 仏滅 | 癸丑 | 間日 |
| 2024年10月17日 | 木曜日 | 大安 | 甲寅 | – |
| 2024年10月18日 | 金曜日 | 赤口 | 乙卯 | – |
| 2024年10月19日 | 土曜日 | 先勝 | 丙辰 | 間日 |
| 2024年10月20日 | 日曜日 | 友引 | 丁巳 | – |
| 2024年10月21日 | 月曜日 | 先負 | 戊午 | 間日 |
| 2024年10月22日 | 火曜日 | 仏滅 | 己未 | – |
| 2024年10月23日 | 水曜日 | 大安 | 庚申 | – |
| 2024年10月24日 | 木曜日 | 赤口 | 辛酉 | – |
| 2024年10月25日 | 金曜日 | 先勝 | 壬戌 | 間日 |
| 2024年10月26日 | 土曜日 | 友引 | 癸亥 | – |
6回目の八専と間日
| 日にち | 曜日 | 六曜 | 日干支 | 間日 |
| 2024年12月14日 | 土曜日 | 赤口 | 壬子 | – |
| 2024年12月15日 | 日曜日 | 先勝 | 癸丑 | 間日 |
| 2024年12月16日 | 月曜日 | 友引 | 甲寅 | – |
| 2024年12月17日 | 火曜日 | 先負 | 乙卯 | – |
| 2024年12月18日 | 水曜日 | 仏滅 | 丙辰 | 間日 |
| 2024年12月19日 | 木曜日 | 大安 | 丁巳 | – |
| 2024年12月20日 | 金曜日 | 赤口 | 戊午 | 間日 |
| 2024年12月21日 | 土曜日 | 先勝 | 己未 | – |
| 2024年12月22日 | 日曜日 | 友引 | 庚申 | – |
| 2024年12月23日 | 月曜日 | 先負 | 辛酉 | – |
| 2024年12月24日 | 火曜日 | 仏滅 | 壬戌 | 間日 |
| 2024年12月25日 | 水曜日 | 大安 | 癸亥 | – |
八専の起源と由来とその意味
八専とは、十干十二支と陰陽五行説を基にした選日のひとつです。古代中国の春秋戦国時代に生まれた陰陽五行思想は、「全ての物事は陰陽に分類できる」という考え方(陰陽道)と「全ての物事は木・火・土・金・水の五つの元素から成る」という考え方(五行説)が結びついています。
陰陽五行説では、木・火・土・金・水に陰陽が存在することから、10個の元素が導かれます。これらは十干と呼ばれ、それぞれ甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸と名付けられています。十干と十二支が組み合わさったものが十干十二支であり、これが八専の割り当ての基盤となっています。
「八専」は同気が重なる8日
八専は、日の干支(十干と十二支)が壬子の日(49番目)から癸亥の日(60番目)までの12日間を指します。この12日間のうち、同じ五行に属する日が8日存在することから「八専」と称されています。「専」は「専一」すなわち同気が重なることを表します。よって、「八専」は同気が重なる8日間を意味します。
具体的には、壬子、甲寅、乙卯、丁巳、巳未、庚申、辛酉、癸亥の8日間が八専に該当します。これらの日は同じ五行(水、木、火、土、金)に属する十干と十二支が重なる日で、それぞれ「水水」「木木」「火火」「土土」「金金」の同気が形成されます。
| 六十干支順位表番号 | 干支 | 五行 |
|---|---|---|
| 49 | 壬子(みずのえね) | 水水 |
| 50 | 癸丑(みずのとうし) | 水土 |
| 51 | 甲寅(きのえとら) | 木木 |
| 52 | 乙卯(きのとう) | 木木 |
| 53 | 丙辰(ひのえたつ) | 火土 |
| 54 | 丁巳(ひのとみ) | 火火 |
| 55 | 戊午(つちのえうま) | 土火 |
| 56 | 巳未(つちのとひつじ) | 土土 |
| 57 | 庚申(かのえさる) | 金金 |
| 58 | 辛酉(かのととり) | 金金 |
| 59 | 壬戌(みずのえいぬ) | 水土 |
| 60 | 癸亥(みずのとい) | 水水 |
八専の間日
間日とは、「まび」と読み、八専の期間内で五行の同気が重ならない日を指します。間日は特に何も影響を受けない平穏な日で、壬子から始まる八専の期間内に存在する50番目、53番目、55番目、59番目の日を指します。
癸丑、丙辰、戊午、壬戌の4日間は同じ五行に属さないため、八専から外れ、「八専の間日(まび)」と呼ばれます。
八専は十干十二支の60日周期に基づいています。一年を365日とすると、一年におおよそ6回の八専があり、その期間は約48日間となります。八専の期間内に五行の同気が重ならない日を間日(まび)と言います。これは特に影響を受けない平穏な日で、壬子から始まる八専の期間に存在する50番目、53番目、55番目、59番目の日を指します。間日は特に凶とされる影響から外れるとされています。
八専と雨
八専の期間は降雨が多いと言われています。特に、八専の2日目は「八専二郎」と呼ばれ、この日に雨が降ると長雨になると言われています。このため、特に農家では八専は厄日の一つとされています。
八専に雨が多い理由として、陰陽五行説において水が重なる日が八専となるため、雨が降る可能性が高いとされています。ただし、これは科学的な根拠ではなく、また一年に6回も発生する八専が毎年雨が多いとは限らないため、これを迷信として扱う方が良いかもしれません。
八専にやってはいけないこと
八専の日は、陰陽五行思想に基づき同じ五行の気が重なることから、物事が一方に偏りやすいとされています。そのため、「凶日」とされ、特定の行動を控えることが勧められています。そのため、引越し、神事、法事、婚約、破壊につながる行為、契約、柱を建てる(土木関連)などを行うべきではありません。特に八専の日は雨が多いとされ、そのため農家にとっては凶日とされています。
八専にやってはいけないこと、法事
八専の日には、特に法事(仏事や供養など)を避けるべきです。仏事や供養は故人を祀る大切な行為であり、その際に不吉な日を選ぶことは敬意を示す上で適切でないとされています。
八専にやってはいけないこと、建物の解体や大規模な改築
建物の解体や大規模な改築などの着手は、八専の日には控えるべきです。このような作業は物理的なバランスを壊す行為であり、凶日である八専の日にはさらなる不均衡をもたらす可能性があるとされています。
八専にやってはいけないこと、結婚
入籍や結婚式などの婚礼も、八専の日には避けるべきです。結婚は二人の新たな生活のスタートであり、その始まりを凶日に行うことは不適切とされています。
八専にやってはいけないこと、針灸
針灸は体内のエネルギーのバランスを調整する手段ですが、そのバランスを調整する行為自体が八専の日の同気の重なりと相まって不調を引き起こす可能性があるため、避けられています。
八専にやってはいけないこと、土木作業、特に柱立て
家を建てる際の柱立てや、それに類する大きな土木作業も避けるべきです。建物の柱はその建物の基盤となる重要な部分であり、その設置を八専の日に行うことは、その建物に不運がもたらされる可能性があるとされています。
八専にやってはいけないこと、神事・参拝・法事
「八専」は神々が地上を離れ、天上へと昇っていると言われています。そのため、この期間に神事、参拝、法事などを行っても、その神々や仏さまのお力が地上にはないため、その意義が薄れると言われています。
八専にやってはいけないこと、引越し
引越しについては、「八専」よりも仏滅や三隣亡、不成就日などの方がより強く影響を与えるとされています。ただし、可能であれば「八専」の期間も避けた方が良いと言われています。
八専にやってはいけないこと、契約などの大きなイベント
契約や重要なイベントについては、縁起を左右する可能性があるため、「八専」の期間は避けることが推奨されています。
八専のスピリチュアル
“八専”という期間は、スピリチュアルな観点からすると感情の浮き沈みが激しいとされています。これを”魔の八専”とも呼ぶ人もいます。しかし、”魔の八専”が全てを否定的なものに変えるわけではなく、極端な状態に引き寄せるという特性があります。つまり、過度に興奮したり、逆に無気力になったりする期間を指します。その結果、この期間は感情的に不安定になりやすいとされています。
八専の時期には前例のない大成功を遂げることもありますが、同様に前例のない大失敗を経験することもあります。特に感情が不安定な状態で、さらに不安定な対応をすると、その結果はしばしば混乱となります。
そのため、この八専の期間中には、自身がどんな挑戦に直面しても、それに対する感情的な反応を抑え、問題を解決することに専念することをお勧めします。つまり、他人から不合理な要求があっても、それに対して過度に反応せず、事態を収束させることに全力を注ぐことが、無用なエネルギーや時間、そして財産を無駄にするのを避ける一助となるでしょう。
また、もし何か問題に直面したときには、「ああ、これが”魔の八専”の効果なのか!」と考え、その挑戦にどう向き合うかを冷静に考えるようにしましょう。その心構えが、”魔の八専”の罠に陥らないための重要なキーとなるでしょう。


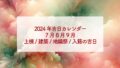


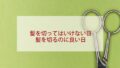


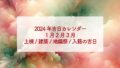

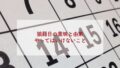


コメント 成功の口コミや疑問…読んでね!