
七月七日ごろは二十四節気で「小暑」と呼ばれます。この時期は七夕様と重なりますね。小暑はまさに「小さく暑い」でこれからどんどん暑くなっていく事を予測させる時期です。
この小暑についてご紹介します。
小暑の読み方
小暑の読み方は「しょうしょ」です。
小暑とは
「小暑(しょうしょ)」は、二十四節気の第11の節気で、毎年7月6日または7日にあたります。二十四節気とは、太陽の黄経を等分し、一年を24の期間に分けたものです。小暑は太陽黄経が105度のときに訪れ、暑さが本格化する時期を意味します。
梅雨明けも近くなり、セミが鳴きだし、湿っぽさの中にも夏の熱気が感じられるようになる時期です。江戸時代の暦の解説書『暦便欄』では、「大暑来れる前なればなり」と記されています。つまり、小暑の次が大暑、つまり最も暑い時期が訪れることを意味します。
例年では、梅雨明けと重なることが多く、日に日に暑さが厳しくなっていく季節です。小暑と次の節気である大暑の期間をあわせて「暑中」といい、相手の健康を気遣って、暑中見舞いを送る時季でもあります。
小暑の計算法: 定気法と恒気法
二十四節気の計算法には主に二つの方法があります。一つは「定気法」で、太陽の黄経が特定の度数になる瞬間を節気とします。小暑の場合、太陽黄経が105度となるのが7月7日ごろとなります。もう一つは「恒気法」で、これは特定の節気(冬至など)から一定の日数後を節気とします。恒気法による小暑は、冬至から約197.84日後、つまり7月7日ごろになります。
小暑の期間2026
小暑は一日だけの節気であるとともに、一定の期間を指す言葉でもあります。その期間は小暑(二十四節気の第11)から大暑(二十四節気の第12)の前日までの約15日間とされています。この期間は暑さが厳しくなる夏の序章であり、昼夜の気温差が激しい日々が続く特徴的な時期です。
2026年の小暑は、7月7日から7月22日に設定されています。翌日の七月二十三日は大暑となります。二十四節気は季節の移り変わりを知るための目安で、その年の太陽の動きに合わせて1年を24等分して決めます。したがって、毎年7月7日頃~7月22日頃にあたる小暑ですが、日付は一定ではなく、1日程度前後することがあります。
夏至 → 小暑 → 大暑の順ですよ!
二十四節気では、小暑の前は昼が一番長くなる「夏至」で、小暑の次は暑さが最も厳しくなる頃の「大暑」となります。つまり、二十四節気の順序は「夏至 → 小暑 → 大暑」となります。
2026年の小暑はいつ
2026年以降の小暑は下記の日程になります。
| 年 | 日時 (UT) | 日本 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 7月6日14:20 | 7月6日 | 7月6日 |
| 2025年 | 7月6日20:05 | 7月7日 | 7月7日 |
| 2026年 | 7月7日01:56 | 7月7日 | 7月7日 |
| 2027年 | 7月7日07:37 | 7月7日 | 7月7日 |
| 2028年 | 7月6日13:29 | 7月6日 | 7月6日 |
| 2029年 | 7月6日19:22 | 7月7日 | 7月7日 |
| 2030年 | 7月7日00:54 | 7月7日 | 7月7日 |
梅雨と小暑
通常、小暑の頃には梅雨明けを迎えるのですが、小暑になっても梅雨に入らない場合には「梅雨入りの特定できず(梅雨入りなし)」となります。つまり、梅雨入りを特定するリミットが小暑ということです。その後、梅雨入りの特定はできないまま、梅雨明けが特定されるというパターンが数年に一度起こることがあります。
小暑の七十二候
「小暑」の「七十二候」です。

初候:温風至(あつかぜいたる)(7月7日〜7月11日頃)
「温風至」は、小暑の最初の七十二候です。 この時期になると、夏の暖かい南風が本格的に吹き始め、いよいよ夏らしい暑さがやってきます。梅雨が終わりに近づき、空気もだんだん重く、夜になっても蒸し暑さが続きます。まさに夏本番への入り口となるタイミングで、体調管理が大切になります。
次候:蓮始開(はすはじめてひらく)(7月12日〜7月16日頃)
「蓮始開」は、蓮の花が咲き始める季節です。 池や沼に大きな葉と一緒に咲く蓮の花は、朝早く開いて昼には閉じるという神秘的な性質があります。泥の中からきれいな花を咲かせる蓮は、「清らかさ」や「成長」「再生」の象徴とされ、仏教でもとても大切にされています。夏らしい風景に癒される時期です。
末候:鷹乃学習(たかすなわちわざをなす)(7月17日〜7月22日頃)
「鷹乃学習」とは、鷹の雛が巣立ちに向けて狩りや飛ぶ練習を始める時期を指します。 猛暑の中でも生き物たちはしっかり命をつなぎ、成長しています。親から独り立ちの術を学ぶ鷹の子どもたちの姿は、自然の中でのたくましい生命力や、成長のドラマを感じさせます。
小暑のスピリチュアル―新しい夏のエネルギーに心を整える
小暑は、夏本番のエネルギーが一気に高まる時期です。この季節は、自然界のリズムや自分自身の内面にも「変化」や「活性化」が起こりやすいタイミング。小暑のスピリチュアルな意味を意識することで、心や運気の流れも良くなります。
この時期は、心身ともに「デトックス(浄化)」のタイミングとも言われます。暑さで汗をかくのは、体の中のいらないものや溜まった感情を手放すサイン。こまめな水分補給とともに、不要な思考やストレスも意識的に流すイメージで過ごしましょう。
また、新しいことを始めたり、気持ちを切り替えるのにもぴったりな時期です。夏のパワーが高まる小暑は、「行動力」や「挑戦する勇気」を後押ししてくれます。目標や夢を改めて見直し、やりたかったことにチャレンジしてみると、良い流れに乗れるでしょう。
さらに、小暑の時期に旬の野菜や果物をいただくことで、自然のエネルギーと自分の運気が調和しやすくなります。 夏野菜の鮮やかな色やみずみずしさは、「元気」や「浄化」、「リフレッシュ」の象徴です。食卓に季節の恵みを取り入れることで、家族や自分の運気も上がりやすくなります。
小暑のエネルギーを味方に、**「不要なものは手放し、新しい流れを受け入れる」**という意識で毎日を過ごしてみてください。きっと心も体も軽やかに、夏のパワーを最大限に感じられるはずです。
小暑にやることする事、暑中見舞い
小暑にやることすることは暑中見舞い、七夕祭りになります。
小暑にやることすること、暑中見舞
「暑中見舞い」は、かつてはお盆の前に直接訪れて贈り物を渡す習慣が進化した形とされています。時代が変わり、直接訪問するのが困難になったため、代わりに挨拶状を送るようになったのが始まりと考えられています。
暑中見舞いを送る時期は小暑から
暑中見舞いを送る適切な時期は、二十四節気の「小暑」から「立秋」の前日までとされています。しかし、異説も存在し、「大暑」から送るという意見や、夏の土用の間に送るという意見もあります。一般的には、この期間でも梅雨の最中には送らず、梅雨が明けてから送ることが推奨されています。
暑中見舞いの書き方
暑中見舞いの日付表記には一定の決まりがあります。具体的な日付を書くのではなく、「〇〇年 盛夏」または「〇〇年 〇月」といった形で表します。これは、具体的な日付を書くと贈るタイミングが遅れた場合に不適切になる可能性があるためです。
立秋以降の見舞い
「立秋」を過ぎると、暑中見舞いではなく「残暑見舞い」となります。これは、立秋が秋の始まりとされており、それ以降の見舞いは夏の残りの暑さに対する挨拶という意味合いが強くなるためです。
小暑にやることすること、七夕
小暑の初日、7月7日は七夕の日とも重なります。「七夕」は古代中国から伝わった伝説に由来しています。牽牛星(彦星)と織女星(織姫)が年に一度だけ会うことを許された日、それが7月7日です。この日に短冊に願い事を書き、笹に吊るす風習があります。七夕飾りや行事食のそうめんを食べながら、星を探してみるのもおすすめです。
七夕と朝顔
7月7日を中心に朝顔市も開かれます。朝顔の中国名「牽牛」は彦星のことを指します。
朝顔は、元々中国原産の花で、遣唐使の時代に薬用植物として日本に導入されたとされています。その中国語名は「牽牛(けんぎゅう)」…これは薬用植物として牛車により大量に運ばれたことに由来します。日本ではこの「牽牛」が彦星となり、朝顔の花自体は織姫に例えられ「朝顔姫」と呼ばれるようになりました。
小暑には浴衣を着て夏祭り
夏は祭りの季節でもあります。夏祭りや花火大会に出かける際には、「浴衣」を着ると、一層夏を感じることができます。浴衣は湯上がりの汗を拭いたり、くつろいだりするためのものから派生し、現代ではおしゃれ着感覚で着られるようになっています。
ちょうどこの小暑の時期は七夕祭りが数多く開催されていますよ〜。
小暑から大暑は暑い🥵
小暑から大暑にかけての期間は、「酷暑」という言葉が示すように、厳しい暑さが続きます。昔の人たちも、夏の暑さには悩まされていたようで、俳句にもその様子が描かれています。現代では、冷房機器を上手に使って、酷暑を乗り切りましょう。とにかく熱中症に注意です。
小暑の食べ物
小暑の食べ物についてご紹介します。
七夕=小暑に食べるならそうめん
七夕と小暑は7月7日となりますので、小暑に食べるべきなのは七夕の行事食そうめんとなります。この日には涼しくて食欲をそそるそうめんを食べて七夕の願いを叶えましょう。

小暑の食べ物――夏の元気をくれる旬の味
小暑の時期は、暑さが本格的になり、夏野菜や果物が豊富に出回ります。旬の食べ物をしっかり摂ることで、体調を整え、夏バテを予防することができます。
この時期におすすめの食べ物は、
- きゅうり
- なす
- トマト
- ピーマン
- オクラ
- ゴーヤ
- 枝豆
- とうもろこし
- ししとう
- ズッキーニ
などの夏野菜です。これらは水分やミネラルが豊富で、体を冷やしたり、失われた塩分やカリウムを補ってくれます。
また、スイカやメロン、桃などの果物も、みずみずしくてビタミンや水分補給にぴったりです。
さらに、小暑の頃は「土用の丑の日」が近づくこともあり、うなぎを食べてスタミナをつける風習も根付いています。うなぎは栄養たっぷりで、夏の疲れを吹き飛ばしてくれる食材です。
旬の食材をバランスよく食べることで、自然のパワーを体に取り入れ、元気に夏を乗り切ることができます


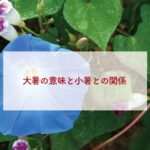
コメント 成功の口コミや疑問…読んでね!