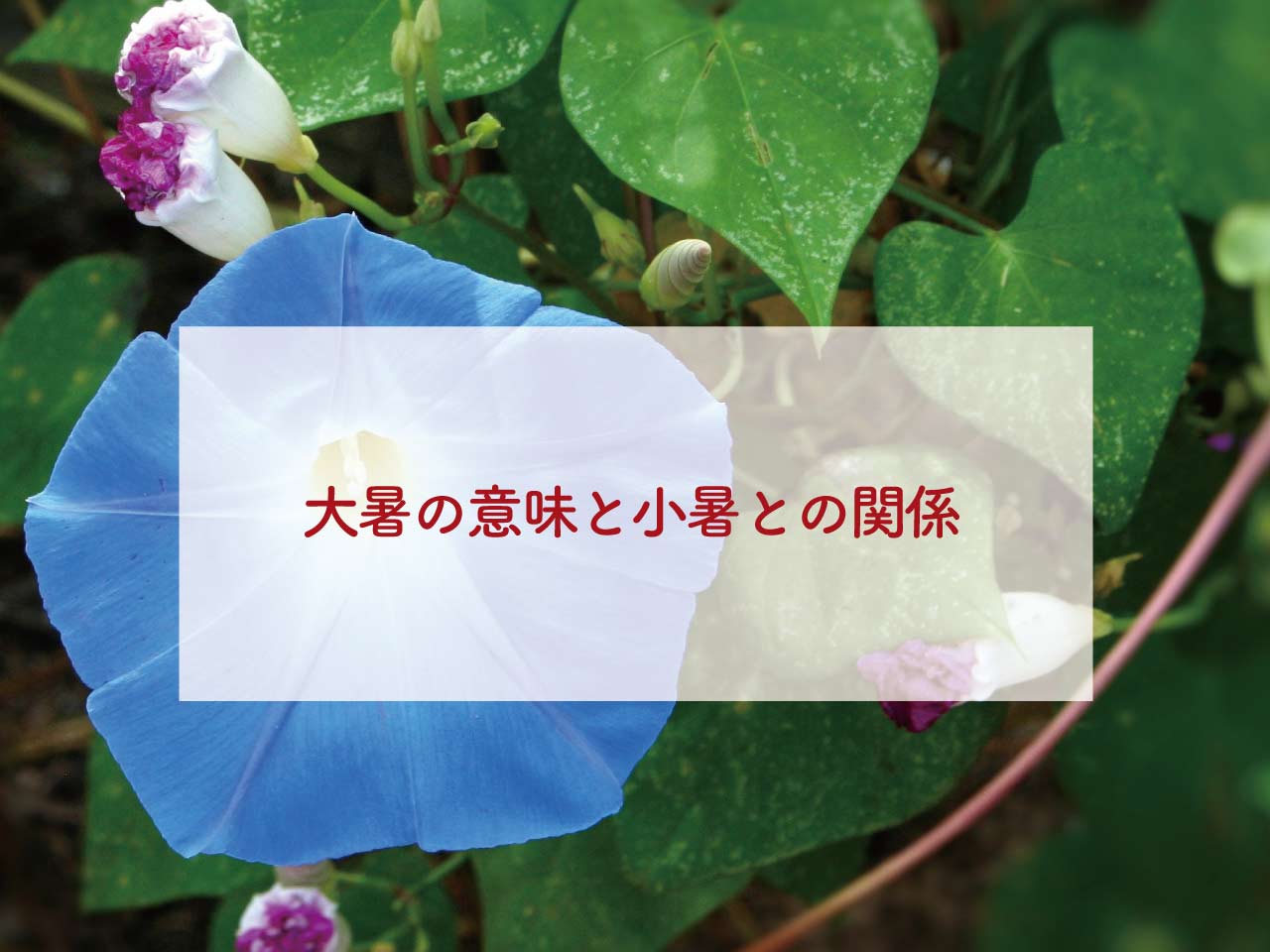
七月も半ばを過ぎれば大暑です。2026年は7月23日が大暑ですね〜。
大暑は土用の丑の日にも近く、まさに「大きく暑い=ものすごく暑い」日々の始まりです。
そして大暑が過ぎればすぐに立秋…暦の上では秋ですね。
大暑とは
大暑は、二十四節気の第12番目にあたる節気で、毎年7月23日ごろから始まります。その名前の通り、「もっとも暑さが厳しくなる頃」という意味を持っています。実際に、梅雨が明けていよいよ夏本番となり、気温が一気に上がるのがこの時期です。田んぼや畑では稲がすくすくと育ち、セミの鳴き声がより一層響き渡ります。
大暑の期間は、例年7月23日ごろから8月6日ごろまでの約2週間です。この時期は「夏バテ」や「熱中症」に気を付ける必要があり、体調管理がとても大切な季節です。昔から、「土用の丑の日」がこの時期に重なることが多く、うなぎを食べてスタミナをつける風習もここから来ています。
また、二十四節気はさらに「七十二候(しちじゅうにこう)」という細かい季節の変化にも分かれていて、大暑の間にも自然の移り変わりが細かく表現されています。桐の花が実を結び始めたり、土が湿って蒸し暑くなったり、大雨が降るなど、まさに「夏のクライマックス」と呼べる季節です。
大暑の読み方
大暑の読み方は「たいしょ」です。
大暑はいつ?
2026年は7月23日が大暑となります。
大暑の期間
大暑はその日1日だけを意味しますが、同時に小暑の終わりから立秋の前日までの期間をいいます。
2026年は7月23日〜 8月7日の立秋までとなります。


大暑と小暑
小暑は大暑のひとつ前、二十四節気の第11番目にあたります。毎年7月7日ごろから始まり、7月22日ごろまで続きます。「小暑」という言葉には、「だんだん暑くなり始める頃」という意味があります。梅雨明けもこの時期に重なることが多く、本格的な夏の入口といえる時期です。
小暑の期間は、田畑の緑が濃くなり、セミの鳴き声が本格的に聞こえ始める季節です。暑さに慣れ始める一方で、まだ夕方や朝方には涼しい風が感じられることもあります。夏の準備期間として、体を暑さに順応させていく大切なタイミングです。
大暑と小暑の違いと関係
ここで改めて「大暑」と「小暑」の違いを見てみましょう。小暑は「暑さが始まる頃」、大暑は「暑さが最高潮に達する頃」と考えるとイメージしやすいでしょう。
小暑から大暑へと季節が進む中で、私たちの生活や自然の様子も大きく変化します。 小暑ではまだ梅雨の名残があることも多く、ジメジメした蒸し暑さや突然の大雨が降ることもあります。一方、大暑になると天気が安定し、真夏の日差しが降り注ぎます。
また、大暑と小暑は連続した時期なので、体調や生活リズムの調整がとても大切です。小暑で体を暑さに慣らし、大暑で体力を維持することが、夏を健康に乗り切るポイントです。農業や漁業でも、この時期に合わせて作業がピークを迎えることが多いです。
大暑の七十二候
大暑の期間は、7月22日から8月6日頃までで、この期間を「七十二候」で細分化すると以下のようになります。
大暑の七十二候、初候「桐始結花」(7月22日〜7月26日頃)
桐始結花桐「きりはじめてはなをむすぶ」:桐始結花桐の花が(来年の)蕾をつける
桐の木が花を結ぶ頃です。桐は日本の夏に代表的な木で、この時期にその花が咲くことを指します。桐の花は華やかで、暑さの中にも自然の息吹を感じることができる、夏の始まりの象徴的な出来事です。
大暑の七十二候、次候「土潤溽暑」(7月27日〜8月1日頃)
土潤溽暑「つちうるおうてむしあつし」:土が湿って蒸暑くなる
土が潤い、湿気が多くなる頃を指します。この時期、夏の暑さがピークに達し、地面が湿り気を帯びることで、空気中の湿度も高くなります。いわゆる「むしむしとした蒸し暑さ」が感じられる時期です。梅雨の終わりから続く湿気が大地にしみ込み、蒸し暑さが一層強くなります。
大暑の七十二候、末候「大雨時行」(8月2日〜8月6日頃)
大雨時行「たいうときどきにふる」:時として大雨が降る
大雨が降る時期です。これにより、夏の猛暑が少し和らぐこともありますが、また湿気が高まり、雷を伴った激しい雨が降ることも多いです。この時期、台風や集中豪雨など、天候が不安定になりやすいのも特徴です。農作物の育成にも大きな影響を与える時期であり、天候が不安定であることが強調されています。
大暑にすること
大暑の時期は、1年で最も暑さが厳しくなるため、昔から「涼」を求めるさまざまな工夫が行われてきました。この時期にするべきことを知ることで、健康に夏を乗り切ることができます。
大暑にすること
まず大切なのは、体調管理です。水分補給や塩分の摂取、栄養バランスの良い食事、そして十分な休息が欠かせません。暑さによる夏バテや熱中症を予防するために、こまめな水分補給と、朝晩の涼しい時間を利用して無理のない運動を取り入れると良いでしょう。
暑さと上手に付き合う知恵――昔の人の暮らし
昔の日本人は、厳しい夏の暑さを乗り越えるためにさまざまな知恵を身につけてきました。たとえば、「打ち水」や「風鈴」「よしず」など、家の中に涼しい風を取り込む工夫がされていました。夕方になると縁側で家族と涼む――そんな光景も大暑の季節ならではです。
また、体に良いとされる夏野菜やうなぎ、梅干しを食べたり、旬の果物で水分や塩分を補給することも大切な習慣でした。これらの知恵は、現代でも熱中症予防や健康管理に役立ちます。
大暑にすること:打ち水
昔の日本の夏の風物詩といえば「打ち水」です。玄関先や道路に水をまくことで、気温を下げ、涼しさを感じることができます。打ち水には、実際に空気中の温度を下げる効果だけでなく、心を落ち着かせるスピリチュアルな意味合いもあります。 地面に水をまくことで、空間の「気」が整い、邪気払いの作用があると考えられてきました。現代でも、打ち水を行うことで暑さを和らげ、心もリフレッシュすることができます。
大暑と暑気払い
「暑気払い」とは、暑さによる体の不調やだるさを取り除き、元気を取り戻すための風習です。昔からこの時期には、冷たい飲み物やかき氷、夏野菜、瓜やスイカ、ところてん、そうめんなど、体を冷やす食べ物がよく食べられてきました。親しい人たちと集まって食事を楽しむことで、心のリフレッシュや人間関係の活性化にもつながります。
また、暑気払いは単なる食事会ではなく、悪い気を払い、新しいエネルギーを取り込むスピリチュアルな意味合いも持っています。現代でも、会社や家族、友人同士で「暑気払い」と称して集まることが多いです。
大暑と土用の丑の日
「土用の丑の日」は、大暑の期間中に訪れることが多い特別な日です。土用の丑の日には、うなぎを食べてスタミナをつける習慣があります。 これは江戸時代から広まった風習で、暑さで体力を消耗しやすい時期に、栄養価の高いうなぎを食べて元気を補うという知恵です。うなぎの他にも、しじみやうどん、梅干し、きゅうりなど「う」のつく食べ物を食べると夏バテしにくいといわれています。
土用の丑の日は、ただの食文化ではなく、「健康と運気のアップ」を願う行事食の側面も持っています。厳しい暑さを乗り越えるための日本人の知恵と、家族や仲間と過ごすひとときを大切にする心が表れています。
大暑の時期には、「土用の丑の日」や各地のお祭り、花火大会など、夏の風物詩が目白押しです。これらの行事は、暑さを忘れさせ、夏の楽しみを提供してくれます。「土用の丑の日」には、体力回復のために鰻を食べる習慣があります。また、特に夕方から夜にかけての花火大会は、涼しい夜風と美しい光景が組み合わさり、夏の魅力を最大限に引き立てます。

大暑の頃の花
大暑の頃には、様々な花が咲き誇り、その美しさで私たちに涼しさや慰めを与えます。二十四節気の一つである大暑は新暦の7月23日ごろで、特にアサガオやオミナエシ、白粉花(おしろいばな)がこの時期に咲くことで知られています。
アサガオはヒルガオ科サツマイモ属に属する植物で、学名はIpomoea nil、英名はMorning gloryとされています。原産地は中央から熱帯アメリカとされ、短日植物であるためこの時期に開花を迎えます。種類は様々で、園芸種の中には変化アサガオなどもあります。種が手に入れば、自分で育ててみるのもおすすめです。
白粉花(おしろいばな)は夕方に開き、翌朝にしぼむ花です。その名前は、少女たちが花の中の白い粉をおしろい代わりにして遊んでいたことからつけられました。
また、オミナエシはスイカズラ科オミナエシ属に属する植物で、学名はPatrinia scabiosifolia、英名はGolden laceとされています。原産地は日本で、秋の七草の一つでもあります。黄色い花が特徴的なオミナエシは、その名前の由来が「女郎花」で、昔は貴族の令嬢や婦人の敬称であった「女郎」と、飯を意味する「エシ」から来ています。
大暑が旬の野菜
大暑の頃はさまざまな夏野菜が旬を迎えます。ここでは暑さを凌ぐためにも水分が豊富でカリウムの含有量の多い野菜をご紹介します。
大暑の丑の日には「う」のつ食べ物
一年で最も暑さが厳しい大暑の時期。暑さで食欲が減退しがちなこの時期、土用の丑の日に因んで、「う」のつく野菜、例えば「うり(冬瓜)」を食べたり、伝統的なうなぎを食べたりすることで、暑さを乗り越えてみてはいかがでしょうか。
代表的な大暑の旬野菜
大暑の時期は、一年で最も暑いと同時に、夏野菜が最も美味しくなる季節でもあります。**旬の野菜は栄養価が高く、体を内側から元気にしてくれるパワーがあります。**特にこの時期は、夏バテ防止や熱中症予防にぴったりの野菜が豊富です。
代表的な大暑の旬野菜には、
- きゅうり
- なす
- トマト
- ピーマン
- オクラ
- ゴーヤ
- とうもろこし
- 枝豆
- ししとう
- かぼちゃ
- みょうが
- ズッキーニ
などがあります。
これらの野菜は、水分やミネラルがたっぷり含まれており、体の熱を冷ましたり、汗で失われがちな栄養素をしっかり補ってくれます。きゅうりやトマト、なすは生で食べても美味しく、さっぱりとした味わいで食欲がないときにもぴったりです。 ゴーヤやピーマン、オクラはビタミンや食物繊維が豊富で、疲れやすい夏の体を元気にサポートします。
また、とうもろこしや枝豆などの豆類は、良質なタンパク質も補えます。冷やし中華やそうめんの具材、サラダ、漬物、炒め物など、工夫次第でさまざまな料理に活用できるのも夏野菜の魅力です。
旬の野菜を食卓に取り入れることで、夏の暑さを乗り越えるパワーをもらえるだけでなく、季節の恵みを体全体で感じることができます。




コメント 成功の口コミや疑問…読んでね!