
激しい暑さは終わり、立秋…秋が来て処暑になりました。
二十四節気の処暑についてです。
処暑とは
処暑は、厳しい暑さがやわらぐ時期を指します。この頃になると、朝夕は涼しく感じられ、心地良い虫の声が聞こえてきます。しかし、一方で台風の季節の到来でもあるため、注意が必要です。
2026年の処暑は、8月23日
2026年の処暑は、8月23日。地域によっては、この頃から心地よい夜風を感じ、長くなる夜を楽しみながら、秋の到来を待ち望むことでしょう。
「処暑」の気候は、昼間はまだ暑いものの、朝夕は涼しい…この時期は外での夕涼みや散歩が特に心地よく感じられることでしょう。
1年を24に区分した季節の目安:二十四節気
8月下旬、まだまだ残暑厳しい日々が続きますね。二十四節気という古来からの季節の区分によれば、この時期は「処暑」に位置します。二十四節気は、太陽の動きをもとにした季節の変化を示すもので、年を24の節気に分け、農作業や行事の目安として使われてきました。
冬至、夏至、春分、秋分などの耳慣れた言葉も、この二十四節気の中から来ています。そして、何月何日「ころ」とされるのは、実際の日付が年によって1日ほど前後するからです。
処暑の七十二候
処暑の七十二候のご紹介です。
綿柎開(わたのはなしべひらく):8月23日〜8月27日頃
この時期は「処暑」の初候にあたります。
「綿柎開」とは、綿の花が咲き終わり、実を包むガク(萼=はなしべ)が開き始めるころを表しています。綿の実は、ガクが開くことで白いふわふわの綿毛が現れます。これは「豊かな実り」や「秋の準備が始まる」自然のサインとも言えます。田畑の作物も徐々に収穫の時期へ向かい、季節が本格的に秋へ向かい始めるタイミングです。
天地始粛(てんちはじめてさむし):8月28日〜9月1日頃
「天地始粛」は、「天地(空と大地)が初めて粛然とする=静かに引き締まり始める」という意味です。
夏の熱気がやわらぎ、大気や地面が少しずつ冷たさを帯びてくる頃を示しています。日中はまだ暑い日があっても、朝夕には涼しい風を感じるようになり、虫の音も秋らしくなっていきます。自然界全体がゆっくりと秋色へと変わっていく、季節の静かな移行期です。
禾乃登(こくものすなわちみのる):9月2日〜9月6日頃
「禾乃登」は、「禾(のぎ、つまり稲や麦などイネ科の植物)が実る」という意味です。
田んぼの稲が黄金色に実り、いよいよ収穫を迎える時期です。農村部では稲刈りの準備が始まり、日本人の主食であるお米の恵みを感じられる季節です。「実りの秋」の到来を象徴する候であり、これまでの苦労や努力が形になっていく、感謝と喜びのタイミングでもあります。
処暑の花
処暑の頃に咲く花々も、スピリチュアルな視点で見ると大切なメッセージを持っています。代表的な花としては「百日紅(さるすべり)」「芙蓉(ふよう)」「萩(はぎ)」「朝顔(あさがお)」などが挙げられます。
百日紅(さるすべり)は、夏の終わりから秋にかけて長く咲き続ける花で、「粘り強さ」「持続」「生命力」の象徴です。色鮮やかな花が長く楽しめることから、「人生を明るく前向きに生き抜く力」を与えてくれるとされています。
芙蓉(ふよう)は、朝に咲いて夕方にしぼむ一日花でありながら、次々に新しい花を咲かせます。これは「再生」や「新しい始まり」のスピリチュアルなメッセージを持ち、処暑の転換点にふさわしい花です。
萩(はぎ)は、秋の七草の一つとしても知られ、季節の変わり目を告げる役割があります。人と人との縁や感謝の気持ちを思い出させてくれる花であり、心の交流やご縁を大切にするタイミングを教えてくれます。
朝顔(あさがお)は夏の花として知られていますが、処暑の時期にも美しく咲きます。「はじまり」「希望」「純粋さ」の象徴で、処暑から秋に向けて新しい気持ちでスタートする後押しをしてくれる花です。
こうした花々を日々の暮らしに取り入れることで、処暑ならではのスピリチュアルなエネルギーや季節の移ろいを身近に感じることができるでしょう。
処暑の食べ物、行事食
処暑の頃は、夏の名残を感じながらも、秋の実りが少しずつ登場し始める時期です。この時期に旬を迎える食材や、昔から伝わる行事食をいただくことは、体調を整えるだけでなく、運気や心のバランスを整える上でも大切です。
代表的な処暑の旬の食材には、なす・きゅうり・ピーマン・とうもろこし・オクラ・ゴーヤ・トマトといった夏野菜がまだまだ美味しいタイミングです。また、枝豆やししとう、冬瓜も今が食べ頃。これらの野菜は、夏の疲れを癒し、体を冷やしてくれる働きがあります。
一方で、いちじく・ぶどう・梨といった初秋の果物も市場に並び始めます。これらは「実り」や「豊かさ」の象徴とされ、スピリチュアル的にも「運気の実り」や「新たなご縁・チャンスの到来」を意味します。新しい季節への移行期にぴったりのフルーツです。
伝統的な行事食とその意味
処暑の時期は、お盆(旧暦の地域ではこの時期)や地蔵盆などの行事と重なることがあります。お盆では家族やご先祖とともに精進料理をいただいたり、きゅうりやなすで精霊馬を作って供え物にしたりします。こうした行事食は「ご先祖や自然への感謝」を表し、心を浄化し運気を整えるスピリチュアルな意味も含まれています。
また、処暑以降は秋の収穫が少しずつ始まるため、「新米」や「秋ナス」「初物の栗や里芋」など、旬の恵みを味わう家庭も増えてきます。初物を食べると「福が来る」と言われるのは、自然のサイクルと自分のリズムを重ねる大切な習わしです。
食事を通して運気を高めるコツ
旬の食材をしっかりいただくことは、体の調子を整えるだけでなく、「自然界との調和」や「新しい運気を呼び込む」ことにもつながります。 彩り豊かな夏野菜と秋の果物を組み合わせて、家族や大切な人と食卓を囲みましょう。食事のたびに「いただきます」「ごちそうさま」と感謝の気持ちを込めることで、さらに運気が上がりやすくなります。
季節の行事食や旬の恵みを意識して取り入れることで、心も体もスピリチュアルなパワーで満たされ、処暑をより健やかに、豊かな気持ちで過ごせるでしょう。
処暑のスピリチュアル
スピリチュアルな観点から見ると、処暑は「浄化」と「転換」のタイミングです。夏の間に溜まった疲れやストレス、不要なエネルギーを手放し、心身をリセットする絶好のチャンスとなります。
また、秋は「実りの季節」とも呼ばれます。処暑は、その豊かさを受け取る準備期間です。自分自身の心を整え、内なる声に耳を傾けることで、これからの季節に大きな収穫を得やすくなります。
心のデトックス
処暑の頃は、無意識のうちに溜め込んでいた感情や悩みを手放すのに最適な時期です。夏の間、我慢していたことや、無理をしていたことはありませんか?処暑の風に当たりながら深呼吸をして、いらないものを吐き出すイメージで過ごしてみてください。
この時期に意識的に心のデトックスを行うことで、気持ちが軽くなり、次のステージへ進む準備が整います。古い習慣や考え方を見直し、不要なものを手放す勇気を持つことが、運気アップにもつながります。
新しい流れを迎える
処暑は「転換点」としての意味も強く持っています。自然界が夏から秋へと移り変わるように、私たちも人生の流れが変わりやすい時期です。新しいチャレンジや決断をするのに最適なタイミングともいえます。心身をリセットした後は、目標や夢に向かって一歩踏み出す勇気を持ちましょう。
処暑におすすめの過ごし方――スピリチュアルなアクション
この時期に心がけたいのは、「リラックス」と「リセット」です。自然のエネルギーを感じながら、心身のバランスを整えることが大切です。
1. 自然の中で過ごす
処暑の涼しい風を感じながら、公園や森、川辺などでゆっくり過ごしてみましょう。自然の中には浄化のエネルギーが満ちているため、心が落ち着きやすくなります。木々の緑や土の香り、虫の音に意識を向けることで、自然と心がリセットされます。
2. 身の回りの整理整頓
季節の変わり目は、身の回りの整理整頓にも最適なタイミングです。部屋の掃除や不要な物の処分を行うことで、滞っていた運気が流れやすくなります。特に玄関や窓周りをきれいにすると、良い気が入りやすくなります。
3. 瞑想や呼吸法で心を整える
忙しい日常の中でも、少しの時間を使って瞑想や深呼吸をしてみてください。処暑の静かな空気を感じながら、心の中を整理整頓していくことで、頭も心もスッキリします。毎日の習慣に取り入れることで、穏やかな気持ちを保ちやすくなります。
4. 感謝の気持ちを持つ
夏が終わり、秋の実りを迎える準備が整うこの時期こそ、身の回りのことや人とのご縁に感謝する時間を持つと良いでしょう。「ありがとう」の言葉を大切にすることで、さらに運気が上がりやすくなります。
風水と処暑――運気アップのポイント
風水の観点からも、処暑は大きな意味を持ちます。気の流れが夏から秋へと切り替わるタイミングなので、住まいのエネルギーを整えることが運気アップにつながります。
例えば、寝具やカーテンを秋らしい色に変えたり、家の中にドライフラワーやススキを飾るのもおすすめです。風の通り道を意識して窓を開けることで、停滞していた気が流れ、新たな運が舞い込みやすくなります。
また、処暑の時期は「金運」や「健康運」を意識したインテリアも効果的です。黄色やゴールドの小物を取り入れたり、観葉植物を飾ることで、豊かさや健康のエネルギーを呼び込むことができます。
体調管理とスピリチュアルなセルフケア
処暑の頃は、暑さと涼しさが入り混じるため、体調を崩しやすい時期でもあります。心身のバランスを整えることが、スピリチュアルな運気アップにも直結します。
この時期は特に「冷え」と「湿気」に注意しましょう。夏の疲れが出やすいので、無理せずしっかり休養をとることが大切です。旬の野菜や果物を取り入れた食事や、軽いストレッチなどで、体を内側から整えていきましょう。
体調が安定すると、心も自然と前向きになり、良いご縁やチャンスを引き寄せやすくなります。心と体、両方をいたわるセルフケアを意識して過ごしてください。
家族や人間関係にも変化が現れる
処暑の時期は、人間関係にも新しい風が吹き込みやすい時期です。夏の間に疎遠になっていた人と再び縁がつながったり、新しい出会いが訪れることもあります。逆に、無理に続けていた関係が自然と離れていくこともありますが、これは次のステージへ進むための必要な変化です。
この時期は、執着や依存を手放し、本当に大切な人との関係にエネルギーを注ぐことが開運につながります。自分の心が本当に求めているご縁を大切にしていきましょう。
願いごとや新しいスタートに最適なタイミング
処暑は、新しい目標や願いごとを始めるのにもピッタリなタイミングです。夏の終わりとともに、過去の自分に区切りをつけ、秋から始まる新しい挑戦へと気持ちを切り替えることができます。ノートや手帳にこれから叶えたいことや目標を書き出してみるのもおすすめです。
また、処暑のころは直感力が冴えやすくなります。普段は思いつかないアイデアがふと浮かぶこともあるので、自分の感覚を信じて新しい一歩を踏み出してみましょう。
処暑の時候の挨拶
8月下旬、夏の終わりを迎え、次第に秋の足音が聞こえてくるこの時期。手紙やメールでの挨拶には「残暑の候」や「処暑の候」を使いましょう。それでは、8月下旬の挨拶と使い方を、分かりやすくご説明します。
8月下旬の挨拶の基本ポイント
- 漢語調と口語調の違い: 漢語調は公式な文書やメール向け。口語調は親しみやすい文面に適しています。「残暑の候」「処暑の候」は、公式な漢語調です。
- 送付日に注意: 送る日付に合わせて挨拶を選びます。8月は大暑、立秋、処暑の三つの節気が含まれているので、それに応じて選ぶのがコツ。
- 季節の気配を感じさせる: 8月下旬は暑さが少し和らぎ、秋の気配も近づいてきます。その変化や残暑の疲れを気遣う表現を取り入れましょう。
8月の挨拶の一覧
- 8月上旬: 「盛夏の候」「大暑の候」
- 8月中旬: 「立秋の候」「晩夏の候」
- 8月下旬~9月上旬: 「残暑の候」「処暑の候」「早涼の候」「初秋の候」
それぞれ下記のような時期になります。
・大暑:7月23日頃~8月7日頃
・立秋:8月8日頃~8月22日頃
・処暑:8月23日頃~9月7日頃
8月下旬の挨拶の具体的な例
公式な場面では「拝啓、残暑の候、皆様いかがお過ごしでしょうか」といった形が適しています。一方、もっと親しい相手には「まだ暑い日が続いていますね。体調には気をつけてください」というような気遣いのある言葉を選びましょう。


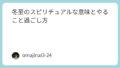
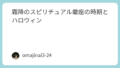
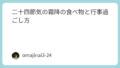
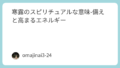
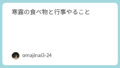


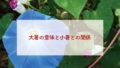

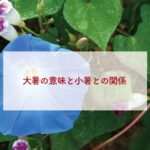

コメント 成功の口コミや疑問…読んでね!